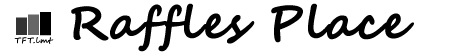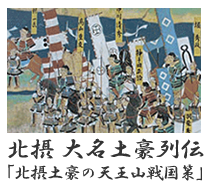[Ⅲ-5] 天下分け目の天王山の戦いにおける中川清秀と高山右近が果たした役割
かたや『天王山』は天下分け目を決定付ける代名詞であるが、羽柴勢が戦略的に重要な天王山を占拠したから戦に勝利したというのは、本当だろうか。
中川史料を参考に『天王山』の真相を探ってみたい。
六月十二日、高山勢は山崎近くに進出した。高山勢を真ん中に中川勢が天王山側、池田勢が淀川沿いを進んだ。兵力は高山勢六百に対し、中川勢三千であった。高山右近に先陣を敷く権限が与えられたとはいえ、たった六百の陣容で第一線を構築することには無理がある。中川勢は中央に陣を敷く高山勢を天王山側と背後から包んでいた。前に張り出した先備えを指揮していたのが中川平右衛門である。そして高山勢の後ろに遊撃隊を率いて古田佐助、後の織部が構えていた。
中川平右衛門は清秀から、先陣を取られた高山勢よりも前に出ろと命じられていた。中川史料に見られる「高山勢からとうせんぼをされた」という描写は、余りにも前に出過ぎた平右衛門隊に対し、右近から、「先陣を預っている高山隊を侵さぬよう慎しまれたい」というような申し入れがあったように受け取れる。もちろんそれが清秀の耳に達するや再度激怒した。そして今度は「高山勢を出し抜いてでも先に開戦の鉄砲を撃ちかけよ」と中川平右衛門に命じた形跡がある。
ところで、清秀と右近は犬猿の仲であったにせよ、中川平右衛門と高山右近は仲が良かったのではないか。平右衛門は清秀の家臣となる以前から、キリシタン信教を通じて高山右近と顔見知りであった可能性は高い。ここで後の説明のために中川平右衛門という人物について述べておきたい。
元の名を田近新次郎と言い、八党盟約衆が中川清秀に推挙した人物である。現在の西宮市と伊丹市の境に田近野という地名がある。
新次郎はこの辺りを地盤にしていた田近党だったが、同国内とはいえ二十キロ以上離れた、決して近くはない茨木の国待と親しかった。新次郎が千提村辺りで催された物珍しいミサを見物にやって来て、キリシタン土豪達と懇意になった可能性は十分にある。伊丹近郊ということは中川や高山党よりも池田や荒木党に近かったと考えられるのだが、新次郎は北摂で少しは名が通っていたようである。
だれもが一度話をすると親しみの湧く人物であったと想像される。彼は清秀の部下となってから、信頼を得てすぐ頭角を現すのだが、後日織田信長に中川清秀が能勢平定を命じられると、その先手に立った。
ところが田近新次郎はほとんど戦わずに任務をまっとうした。彼は攻めるべき砦・城門に立つと篭城主と話し合いをし、現下の情勢と誠実に相手の利を説いて開門に応じさせたのであった。その過程で、ある城主から開門の条件として新次郎が城主の名を貰うという珍事があった。彼は慎んでその名を受け、以後田近平右衛門と名乗った。能勢平定が終わった時、織田信長は彼の手腕に感服し、平右衛門に今度は主家の中川姓を名乗らしめた。
だが三十年後、摂津を遠く離れた豊後臼杵城外で、銃弾に斃れる運命が待っている。
さて話は開戦前日の十二日に戻るが、中川史料によると清秀の陣幕で軍議があり、今晩の内に天王山を占拠してしまう策を採用した。今度の合戦は必ず、天王山を押さえた方が勝利を得るだろうし、おそらく光秀勢も天王山をいち早く奪い取るに違いないと考えた。
そして中川勢総数三千人の内六、七百人がその作戦にあたり、天王山を登りはじめ、夜の内にその頂上を占拠していた。ところが記述からすると、この別働隊は中川譜代の家臣よりも、外様新参の寄せ集めで構成されていた。
本能寺の変が摂津、河内に知れ渡ると、国人・土豪衆はそれぞれ明智方と反明智方のどちらに与みするのかを考えた。河内の三箇サンチョは明智方を選んだ。そして中川清秀に身を託すことにした摂津衆も大勢いた。彼らが有り合わせの武具を引っさげて、三々五々清秀の陣に馳せ参じて来たらどう対処するだろうか。中川正規軍の備えの中に彼らを押し込むことは統制を乱すことにも成りかねない。そこで一石二鳥と彼らをまとめて山に登らせた観がある。安威三河守を筆頭に安威党、上党の面々の名前が散見されることから、八党盟約衆は天王山奪取部隊に加わっていた。
夜が明けて開戦直前の羽柴秀吉方の陣立を俯瞰してみると、左翼は天王山に安威三河守、山麓前線に中川平右衛門、中央に高山右近、そしてそのすぐ後に古田佐助という配置を想定できる。天王山の部隊の中に羽柴秀吉から、目付けとして派遣された安威了佐も混じっていたのではないか。了佐としても中川勢の後方に陣を構える秀吉本陣に居るよりも天下分け目の戦いの最前線に展開する党首安威三河守や顔なじみの八党盟約衆の土豪達とともに、歴史の動く様を最前線で目撃したいと思っただろう。
そしてこの組み合わせは右近にとって、彼らならば寡兵で先陣を務める高山勢を支えてくれると、心強く思えたのではないだろうか。何故なら彼らは、摂津において高山父子と共にキリシタンの教えに誰よりも早く共感を示した人々だったからである。
天王山を明智勢の登る姿が見え隠れし出した。そして八部ほどに達しようとした時、突如天王山の頂上にどよめきとともに中川クルスの旗が林立した。それを合図とするかのように山麓の中川平右衛門隊が鉄砲の火蓋を切った。右近は平右衛門に先に口火を切ることを譲った。明智勢も応戦の火蓋を切った。それが鳴り止むと同時に、高山右近隊と古田佐助隊が敵方の先陣、斉藤内蔵助隊とぶつかり乱戦模様となった。天王山全体が割れんばかりの射撃音に包まれた。後から競うように昇り上がってきた羽柴勢の圧倒的な鉄砲の数に、中腹の明智勢は圧迫されて後退し始めた。この時とばかり羽柴勢は怒濤のごとく天王山の斜面を攻め下りだした。そして明智勢は敢え無く山麓に転がるように落ち下り、そこに待ち構えていた中川勢に討ち取られた。明智勢は全線に亘って後退し始めるや、中川勢の後方に布陣していた羽柴秀吉正規軍二万が動き出した。そして明智勢はみるみる四分五裂し、壊乱状態に陥った。
天王山に立ち靡いた多数の中川クルスの旗指物は、淀川との間の平地に展開する羽柴勢を大いに勇気付けたことは想像に難くない。逆に明智勢は精神的圧迫感を覚えた。
洞ヶ峠から弁当持参で成り行きを眺めていた大勢の野次馬・群集も、平野での戦況はもうひとつ良く判らないが、天王山に林立する旗を見て、羽柴秀吉勢の勝利を確信した。
当事者ではなく、傍観していた第三者の強い印象から、以後『天王山』という言葉が人口に膾炙した。
つい五年前、足利義昭の都落ちに付き合わされて命運尽きかけた八党盟約衆であったが、戦国きっての晴舞台に勝者として立ち、明智勢の名だたる武将の首級を挙げた。
その時の興奮と高揚はいかばかりであっただろうか。八党盟約衆の一人上源助は、天王山頂上から目撃した天下分け目の色鮮やかな両軍の激突を末裔に語り伝えた。山崎の合戦は戦国時代の遅参者ともいえる摂津衆を一気に歴史の桧舞台に押し上げた。
安威了佐も大きな武功を認められて、摂津代官の資格を得た。