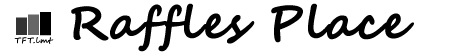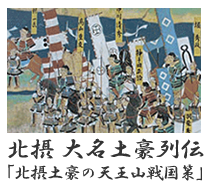[Ⅲ-3] 中川清秀と中川党
中川清秀
中川党は、摂津島下郡中河原、現在の茨木市中河原あたりの豪族であった。足利義晴の治世時に、高山党から佐渡守重清が中川氏の婿養子に入った。そして誕生したのが瀬兵衛尉清秀である。清秀は十五歳にして、池田筑後守勝政の旗下に属したが、彼の武勇によって徐々に家勢を盛り返した。
永禄十二年、三好勢一万余が将軍義昭の居た本国寺を囲んだ際、公方勤仕の和田惟政、伊丹雅興らの摂津衆とともに桂川で三好勢と戦った。その中に盟約八党も混じっていた。
戦いは摂津勢に不利となり、嵯峨へ引き退いたが、清秀は足利御家人衆らと、その夜、四条大宮より掛かって、本国寺を取り巻いた。三好勢を激戦の末、三条の方へ引き退かせ、清秀らは本国寺を奪還した。この働きにより中川清秀は京洛で名を上げた。
元亀元年、荒木村重は信濃守を名乗り池田に入城した。そして従わぬ者は打ち滅ぼすという挙に出、清秀はその先手となり、処々で城攻めをした。
既に将軍家と織田信長と不和に成りつつあった頃、摂州生え抜きの荒木村重と新参の和田惟政の間で、争いが絶えなくなり、ついに島下郡白井河原において雌雄を決する。
開戦直前に荒木村重は立て札に「和田惟政の首を討ち取った者には呉服台五百貫を与える」と布告した。それを見た清秀は即座にその立て札を引き抜き、「俺がもらった」と叫んだという。彼は何か秘策を持っていたのだろうか。
決戦場となった白井河原は、現在の中河原と呼ばれる一帯であることから、清秀にとって隅々まで知り尽くした地元であることは間違いない。
合戦の様子を伝える幾つかの記録はあるが、村重側が三百丁の鉄砲を集めていたことに注目したい。受洗を目前にして、クルスを化粧した前立の冑を被った和田惟政の騎馬を先頭に、二百の兵が、おびき出されるように白井河原に押し出してきた。待ち伏せていたのは、予想をはるかに越える鉄砲であった。恐らく銃声は百丁づつ三度鳴り響き、白井河原は元の静寂が戻った。そして和田勢は敢え無く全滅した。この手柄により清秀は、茨木城下六万石を手に入れた。またこの時、惟政の甲冑に付けられていたクルス紋を継承し、後の中川クルス紋の原型となったと伝わっている。
和田合戦の時、高山飛騨守と右近は惟政に与みした。惟政討ち死に後は、惟長を立てて高槻に篭城した。日本の王都の副王とまで海外に紹介されていた和田惟政のあっけない戦死は、足利義昭と織田信長を驚かせた。信長は明智光秀らを高槻救援に派遣し、ようやく荒木村重らの池田勢は退却したが、信長の脳裏に天下の勇将を鉄砲の一斉射撃で撃ち伏せた中川清秀がしっかりと焼きついた。そして信長はこの戦をヒントに新たな戦法を考え始めていた。信長・家康連合軍が武田の騎馬軍団を三千丁の鉄砲隊による間断の無い一斉射撃で打ち破る長篠の戦法が何のモデルも無しに、突如編み出されたはずは無く、その前例を求めると白井河原の戦いで中川清秀の採った戦法に行き着く。