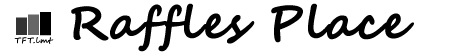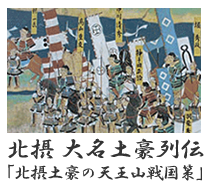[Ⅲ-2] 八党盟約衆
徒党を組むという言葉があるが、これはこの集団に相応しい言葉である。
淀川に近い茨木城下から北へ丹後亀岡に抜ける街道がある。国境の峠の名前から清阪街道と呼ばれているが、現在この道の周辺で、摂津の山間に掛かるあたりから順に安威城・福井城・栗栖山砦,佐保城・大岩城・泉原城の跡が確認されている。どれも十六世紀半ばの城砦であるが、これらが八党の根城であった。一党ではひ弱であるため、いつの頃からか盟約を結んで徒党を組んでいた。これらの領域のほぼ中間位置にある栗栖山砦跡が一九九九年発掘されたが、山の南斜面に中世の大規模な墓地を構えており、この周辺のコミュニティ的な場所であったと見られている。砦は十七の曲輪といたるところに石垣の跡や虎口と呼ばれる出入り口も判明した。この小山がいつからクルス山と称されているのか不明であるが、豊後竹田の八党衆の末裔に、この山に関わりのある伝承がある。八党衆の盟主は、最大の知行地を持っていた安威党である。クルス山の直南に安威村があることから、この山城が安威党の勢力下にあったと考えてまず間違いない。
八党の末裔に共通する伝承として、元室町家人あるいは室町家勤仕であったとしている。
ここで「室町家勤仕」の意味するところであるが、中川清秀は家勢が傾いていた折、摂津伊丹の池田氏の旗下に加わったが、家勢を盛り返した後に再び「室町家勤仕」に戻ったと記されている。このことから他家の支配を受けない独立した国人土豪が、領地安堵の拠り所として、室町家の求める勤めに服するかわりに「室町家勤仕」を称したと想像される。
日々、室町家に出仕していた訳ではなく、室町家から召集が掛かれば出向かねばならなかったと考えられる。この室町家との関係は京に近いが故にできたものであろう。
つまり八党衆も周辺の勢力を持つ国人から独立する拠り所として、「室町家勤仕」を称えていた。定期的に京に上って室町政庁を訪れ、貢物を差し出して、代わりに些細な御用と天下の情報を仕入れて戻ってきては、徒党を集めて用務の役割を決めるというようなスタイルではなかったか。そんな八党衆の近隣で十六世紀半ば以降勢力を伸ばしていたのが、高山党と中川党であった。