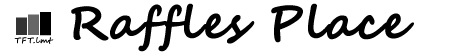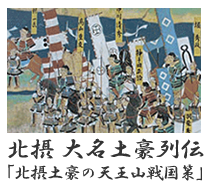[Ⅲ-4] 高山右近と高山党
高山飛騨守と右近
高山姓はありふれた苗字の一つである。フロイスは「日本史」の中で、ジョスト高山右近の一族は摂津の北方のハイランド地方の出身であると記している。この表現から想像するとかなり遠方の標高の高い地方を想像するが、実際は八党盟約衆の領域の北西側に隣接する低い山並が“高山”にあたる。その山並を越えたところに現在でも静かな佇まいの摂津高山郷が残っている。高山党はここに砦を構えていた。
豊後竹田の旧中川家臣団の中にも高山姓を名乗る末裔が存在する。そしてこの高山氏のルーツを辿るとやはり摂津高山村近隣に行き着く。では豊後高山氏と高山右近とはどのように結びつくのだろうか。四百年前の摂津高山党に関わる名前として、右近重友の他に父・飛騨守重房、重房の兄弟重清、祖父重利がある。さらに高山総吉、高山門内も記録に残っている。この中で重清は継嗣の絶えた中川氏の入り婿となり、豊後岡藩の始祖と仰がれた清秀の父となった。総吉は近江志津ケ岳において、その清秀とともに戦死している。高山門内は、荒木村重謀反の際、織田信長側に降伏することを潔しとせず、右近と快を分かって村重側に与みし、足軽大将として摂津池田城に篭城の末、大手門外で戦死した。この経緯から高山総吉・門内らは、高山飛騨守・右近とは別の道を歩んだことが判る。豊後竹田高山氏はこの系統の末裔と考えてよい。
さて高山飛騨・右近父子が戦国大名に成り上がり、キリシタンの柱石として有名になってからは、疑うこともなく飛騨守重房が高山氏の嫡子であったとして語られている。次男重清が養子に出されたのだから、残る兄弟の重房は嫡男であるという推論である。
しかし、重清の嫡男の清秀が、重房の嫡男右近重友より十歳も年上であることに、不自然な点がある。右近は一五五二年、父重房二十五歳の時に生まれている。それから逆算すると一五四二年に生まれた清秀は、重房の弟重清が元服前に儲けたことになる。
それに重清の次男説は変わらないが、長兄の名を石見守重晶と書かれた古文書がある。
石見守は彼らの父重利も名乗った官名であり、長兄が父から引き継いだと考えられる。
高山重房は三男か四男であり、別に摂津高山の総領を継いだ男が存在したのではないだろうか。実はそう考えると、元亀三年(一五七二年)に起こった、高山父子が深く関わり、摂津国を二分する戦いとなった白井河原の合戦の経緯が理解し易い。
目ぼしい相続もできなかった高山重房は、戦国の世を好機と捉え、大望を抱いて故郷摂津高山郷を後にして、京へ向かった。そして当時頭角を現わしてきた三好長慶の祐筆、松永久秀の知遇を得た。京で人脈を作るには大枚の金が必要であるが、故郷の重利が欠かさず仕送りを続けた。その金銀の出所を探ると中川氏の財に突き当たる。中川氏が元の中河原に逼塞してゆくのと反比例して、高山重房は京での人脈を広げ、将軍家馬廻り役であった近江甲賀の名族和田惟政とも近づきになった。
ところでルイス・フロイスは「日本史」の中で、「清秀は右近の敵である」と記録した。
中川史料集においても高山氏と右近の評価は低い。それどころか「重清の婿入り後、高山一族が中川氏の領地や財産を横領し、元の摂津中河原の知行を残すばかりまで衰微してしまった」と、恨みのこもった描き様である。両氏は右近と清秀の代に、幾度も境目争いを繰り返すが、その大元には過去の財にまつわる捩れた問題があったと推測される。
永禄元年(一五五八年)、高山飛騨守重房は、松永久秀から大和沢城主に抜擁された。永禄八年(一五六五年)、将軍義輝横死事件の時、重房は松永久秀の家臣として沢城を守っていたが、落城し摂津高山に戻っていた。
しかし同年七月、後の将軍足利義昭となる一乗院覚慶は密かに南都を脱出し、近江甲賀郡の豪士和田伊賀守惟政の城に逃げ込んだ。
和田惟政は幕府の供回りを務めていて細川藤孝と共に、義昭の旗揚げに果たした役割は大きかった。その論功として、京都所司代に任ぜられ、摂津芥川城主となった。
次いで高槻城四万石を与えられたとき、高山飛騨守を呼び出して家老とした。
懇意にしていた和田惟政の懐に足利義昭が転がり込んできた御蔭で、大和沢城を失い逼塞していた高山重房に運が再び巡ってきた。
しかし摂津に所領を得たことが惟政にとっては後に凶と出る。伊丹や池田といった摂津衆にしてみれば惟政は新人であり、入国当初から反目しあうこととなった。
惟政は飛騨守を通じてキリシタンに並々ならぬ関心を示し、ルイス・フロイスらが信長に謁見できるように取り計らい、京都開教を実現するのに貢献している。
元亀三年(一五七二年)、島下郡白井河原において荒木村重と和田惟政が戦った。
戦いの模様は“中川清秀”で述べたので割愛するが、清秀と高山父子は敵味方に分かれ、それまで表面に出ていなかった両氏の反目を決定的にした。ダリヨ高山飛騨守にしてみれば、キリシタン信仰上大事な盟友の首を清秀が討ち取り、あまつさえ惟政が愛着していたクルス紋まで、甲冑から奪い取ったことに許しがたい憤怒を覚えたことであろう。
その義憤は息子の右近にも継承されてゆく。
しかしこの時、高槻城を取り巻いたのは、中川清秀だけではない。高山氏は大多数の摂津衆を敵にまわして、摂津の外の勢力に与みしたのであった。安威党を盟主とする八党衆もこの時どちらにつくかの選択を迫られた。一方は将軍家と京都所司代をバックとする高山氏、もう一方は摂津ナショナリズムを代表する荒木村重と中川清秀である。そして彼らは清秀を選んだ。この判断は結果的に見て正しかった。
筆者はこの騒動の発端に高山重房・右近父子が深く関わっているように思えてならない。
故郷に逼塞していた高山重房は和田惟政に引き立てられて、いきなり高槻四万石の城代として返り咲いた。このことで高山氏に対し、深い確執の念を有する中川清秀は大きな脅威を感じたのではないだろうか。そして両者の抗争に清秀は荒木村重を、重房・右近は和田惟政を巻き込んでいった。またこの騒動の時、元々の地摂津高山郷に居た高山別派は重房・右近と快を分かち荒木・清秀側についたと考えられる。周りの摂津衆とともに摂津国人として生きる道を選んだ。
その後、高槻城内では、惟政の継嗣惟長派と高山派の主導権争いが生じた。惟長と高山父子とが反目しあうようになる中で、高山父子が荒木村重に通じた。一時敵になったとはいえ、村重の母と飛騨守重房は姉弟である。それに右近と村重は直接的な争いの種を持たず、清秀ほど仲が悪くもなかったと考えられる。惟長派と高山派は、とうとう城内で衝突した。
荒木村重と同盟した重房が高槻城を乗っ取り、まもなく右近が家督を継いだ。
高山氏は父子三代にして、一土豪から二万石を領有する戦国大名にまで登りあがった。
地元の摂津衆を踏み台とし、外部の有力者と組み、最後は文字通りの下克上を実行して主家を討ち、手に入れた。
この歴史的事実に基づく高山氏に対する記憶は、高山氏の周辺に存在した摂津衆の末裔に、時空に横たわる洞窟の最奥から聞こえる微かな残響として、明治中頃までは残っていた。右近高山氏は最後には海外追放という劇的な形で滅び去ったが、豊後高山氏及び高山氏の近隣に居た他の国人土豪の多くが、中川氏の家臣として明治維新を迎えるまで命脈と記憶を保ちえていたからである。
摂津キリシタンを語る場合、高山右近の高槻領での様々な事績が有名であるが、高山氏が旧主和田惟長を放逐して、名実ともに高槻城主となり領内で布教に努めるのは天正元年(一五七三年)以降のことである。高槻領ではなかった清阪街道沿いの八党盟約衆の地域でも同時期にキリスト教は広まったが、領内に持ち込んだ人物として、高山右近と親交の深かった安威五左衛門了佐が有力である。発掘されたクルス山城が安威党の勢力下にあったと述べたが、安威了佐と高山右近がじっこんの間柄であったことから、この城山がクルス山と呼ばれるようになった経緯には、高山右近も関与したことが十分考えられる。